
行政書士
神永 直樹
誰に相談したらよいかわからない悩みの相談相手として、トラブルを未然に防ぐことで、地域で孤独を感じたり、孤立したりすることなく、誰しもがコミュニティの一員であることを実感できる地域作りをサポート。
[相続手続き業務]
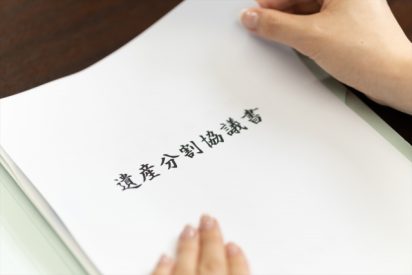
遺産分割協議書は専門家に依頼せず、自分で作成することも可能です。この記事では、遺産分割協議書を作成する際に起こりがちな勘違いや、正確な書き方を分かりやすく解説します。自分で作成することで費用を抑えつつ、安心して手続きに臨む方法を知りましょう。
目次
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割に同意している場合に作成される書類です。この書類は専門家に依頼するイメージが強いかもしれませんが、実際には法律の知識がなくても自分で作成することが可能です。特に、親世代が高齢になり、相続の準備を考え始める中高齢の方にとって、自作することを勉強しておくことは近い未来にの備えになります。その結果、費用を抑える有効な手段となります。
ただし、注意点もあります。遺産分割協議書が法律的に有効であるためには、記載内容や形式が適切である必要があります。形式に不備がある場合、法的効力を持たず後々のトラブルにつながる恐れもあるため、慎重に進めることが大切です。
まずは、自作する際のメリットとその注意点について具体的に見ていきましょう。
遺産分割協議書を自分で作成する最大のメリットは、専門家に依頼する費用を大幅に節約できる点です。司法書士や弁護士、行政書士に依頼する場合、数万円から数十万円の費用がかかることがありますが、自分で作成すればこのコストを削減できます。特に、相続財産が比較的少ないケースや、複雑なトラブルがない場合には、自作が適していると言えるでしょう。
また、自分で作成することで、遺産分割に関する各相続人の意見を直接確認しながら進められるのも利点の一つです。この過程を通じて、相続人間の合意形成がスムーズに進むことも少なくありません。さらに、作成の手順を理解しておけば、将来的に同様の手続きが必要になった際にも役立ちます。
ただし、費用を抑えられるというメリットに目を向けるあまり、記載内容に不備があっては元も子もありません。次のセクションでは、勘違いしやすいポイントや注意すべき点を詳しく解説します。
遺産分割協議書を自分で作成する際、多くの人が陥りやすい勘違いや注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、手間やトラブルを回避できます。
まず、「どのような形式でもよい」と考えるのは誤りです。遺産分割協議書は法的効力を持つために、決められた形式や記載内容を守る必要があります。特に重要なのは、相続人全員の署名と押印が必要であり、この押印には実印を使用する必要がある点です。認印では法的効力を持たないため、実印が用意できていない場合は事前に準備を進めておく必要があります。
さらに、遺産分割協議書には、印鑑証明書の添付が求められることも重要なポイントです。この書類は、各相続人が自分の意思で署名押印したことを証明するために必要とされます。印鑑証明書がない場合、協議書自体が無効になる恐れがあるため、事前に各相続人に取得を依頼しておきましょう。
また、遺産の具体的な分配方法について記載が曖昧だと、後々トラブルになることがあります。たとえば、「不動産は兄が相続する」という表現ではなく、不動産の正確な地番や住所を明記することが必要です。また、銀行口座や有価証券についても、具体的な情報を記載しておくことが重要です。
さらに、「すべての相続人が合意していない場合でも、多数決で決められる」というのは誤解です。遺産分割協議書は相続人全員の同意がなければ成立しません。一人でも同意していない場合には、法的に無効となるため注意が必要です。
このように、自作する際には形式や記載内容に関するルールをしっかり守ることが求められます。次のセクションでは、実際の作成手順について詳しく解説していきます。
遺産分割協議書を作成する際は、手順をしっかりと把握して進めることが重要です。以下では、実際の作成手順を詳しく解説します。
まず初めに、相続人全員で遺産分割の内容について話し合い、合意を形成します。この段階では、各相続人の意見を丁寧に聞きながら調整を行い、全員が納得できる内容を決めることがポイントです。
その後、戸籍を収集し相続人を確定します。下記の記事をご参照ください。
また遺産を調査し、遺産目録にまとめることが望ましいです。
次に、遺産分割の内容を文書にまとめます。ここでは、以下の情報を漏れなく記載することが求められます。
記載内容を整えたら、全員で文書を確認し、問題がないことを確認したうえで署名と押印を行います。この際、実印を使用することが必須です。また、全員分の印鑑証明書を添付する必要がある点にも注意してください。印鑑証明書は最新のものを用意することが望ましく、発行から一定期間が経過している場合には金融機関の求めによっては再度取得をが必要になりますのでご注意ください。
最後に、完成した遺産分割協議書は、相続人の人数分作成し、各相続人が一部ずつ保管します。作成した書類は将来的に必要になる場面も多いため、厳重に保管しましょう。特に、不動産の名義変更や預貯金の解約などでは、遺産分割協議書が必須となるため、書類が法的に有効であることを確認してから使用するよう心がけてください。
正しい手順を踏むことで、遺産分割協議書を自分で作成することは十分可能です。次のセクションでは、専門家に依頼する場合との違いについて触れていきます。
遺産分割協議書を自分で作成する場合と、専門家に依頼する場合では、費用や手間、安心感の面で大きな違いがあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。
まず、費用の面では、自分で作成する場合は大幅なコスト削減が期待できます。専門家に依頼する場合、司法書士や弁護士の報酬として数万円から数十万円かかることが一般的です。一方で、自作の場合はほぼ無料で作成できます。ただし、印鑑証明書の発行手数料や郵送費などのわずかな費用は必要となります。
次に、手間の面では、自作には相続人全員との話し合いや書類作成、形式確認といった作業が求められます。一方で、専門家に依頼すれば、これらの手続きをほとんど任せることができるため、スムーズに進められるのがメリットです。ただし、必要な情報を専門家に伝えるための準備は必要となります。
最後に、安心感という点では、専門家に依頼する方が確実です。遺産分割協議書が法的に無効となるリスクを避けたい場合や、記載内容が複雑な場合には、専門家の知識や経験を活用することが推奨されます。また、相続人間で意見がまとまらない場合にも、第三者として専門家が仲裁に入ることで解決が容易になることがあります。
自分で作成するか、専門家に依頼するかは、相続財産の内容や相続人間の関係性、費用面の優先度によって選ぶのが良いでしょう。いずれの場合も、自分たちの状況に合った方法を選ぶことが重要です。
遺産分割協議書は、相続人全員が合意すれば、自分で作成することが可能です。自作することで専門家に依頼する費用を大幅に抑えられるのが大きなメリットですが、その一方で、形式や記載内容に不備があると法的に無効になるリスクもあるため、注意が必要です。
また、遺産内容や分割方法を正確に記載することが、トラブルを避けるための基本となります。これらのポイントを押さえ、正しい手順で作成することで、自分で遺産分割協議書を作成することは十分に可能です。
ただし、相続財産が複雑だったり、意見の対立がある場合には、専門家の力を借りることでスムーズに進めることができます。自分に合った方法を選択し、相続手続きを円滑に進めましょう。
普通のコピー用紙でいいのか?
遺産分割協議書は、普通のコピー用紙でも便箋でも問題ありません。法的には特定の用紙が求められているわけではありませんが、耐久性や保存性を考慮して、質の良い用紙を使用することをおすすめします。また、内容が変更されたり改ざんされたりするのを防ぐため、手書きで作成する場合でもしっかりと署名押印を行いましょう。
紙のサイズに指定はある?
遺産分割協議書の紙のサイズについても法律上の決まりはありません。ただし、一般的にはA4サイズかA3サイズが推奨されます。これは、保存や提出がしやすく、書類として扱いやすいサイズだからです。
何枚になってもいいの?
遺産分割協議書が何枚になっても問題ありません。ページ数が多くなる場合は、各ページに割印を行うことで書類の改ざん・差し替えが行われないように注意することが必要です。全体を製本テープで一冊の冊子のようにまとめ割印をすることも一つの方法です。
みんなが集まって話す必要があるのか
相続人全員が一堂に会して話し合うのが理想的ではありますが、必ずしも集まる必要はありません。電話やメール、オンラインミーティングを活用して、各相続人と意見を交わす方法でも問題ありません。重要なのは、全員が遺産分割の内容についてしっかりと合意していることです。
ただし、最終的に遺産分割協議書に署名と実印を押す際は、各相続人が同意を明確に示す必要があります。このため、全員のコミュニケーションが円滑に取れる方法を選ぶことが大切です。顔を合わせて話し合うことで誤解を防ぎやすくなる場合もあるため、可能なら集まる方向で検討するのがおすすめです。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。
対応地域
神奈川県(川崎区)・東京都・その他全国オンライン対応